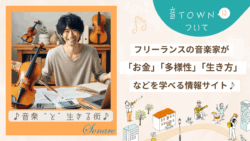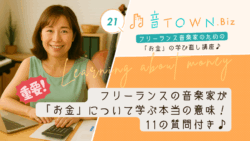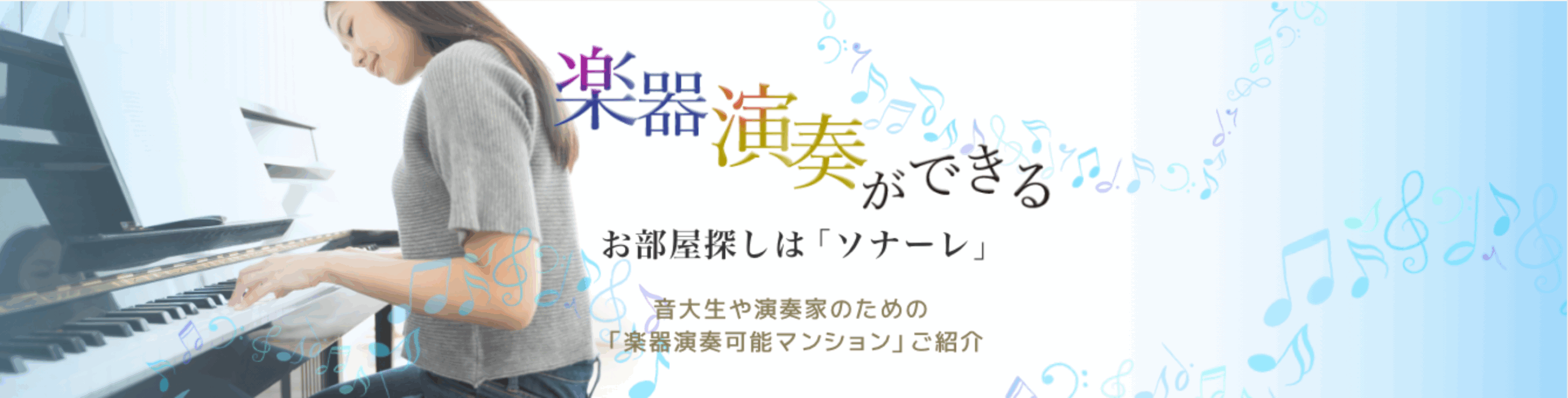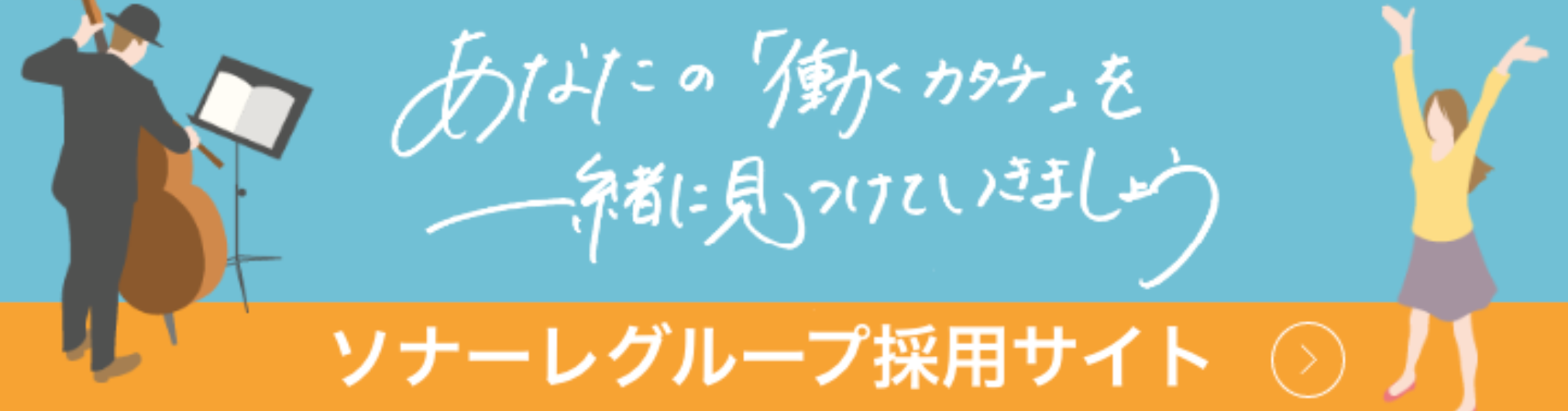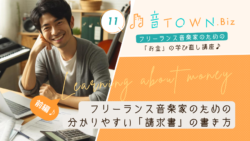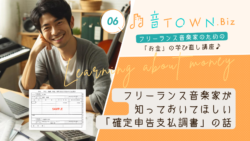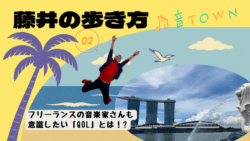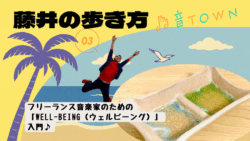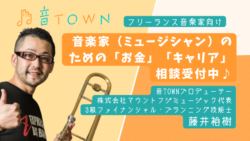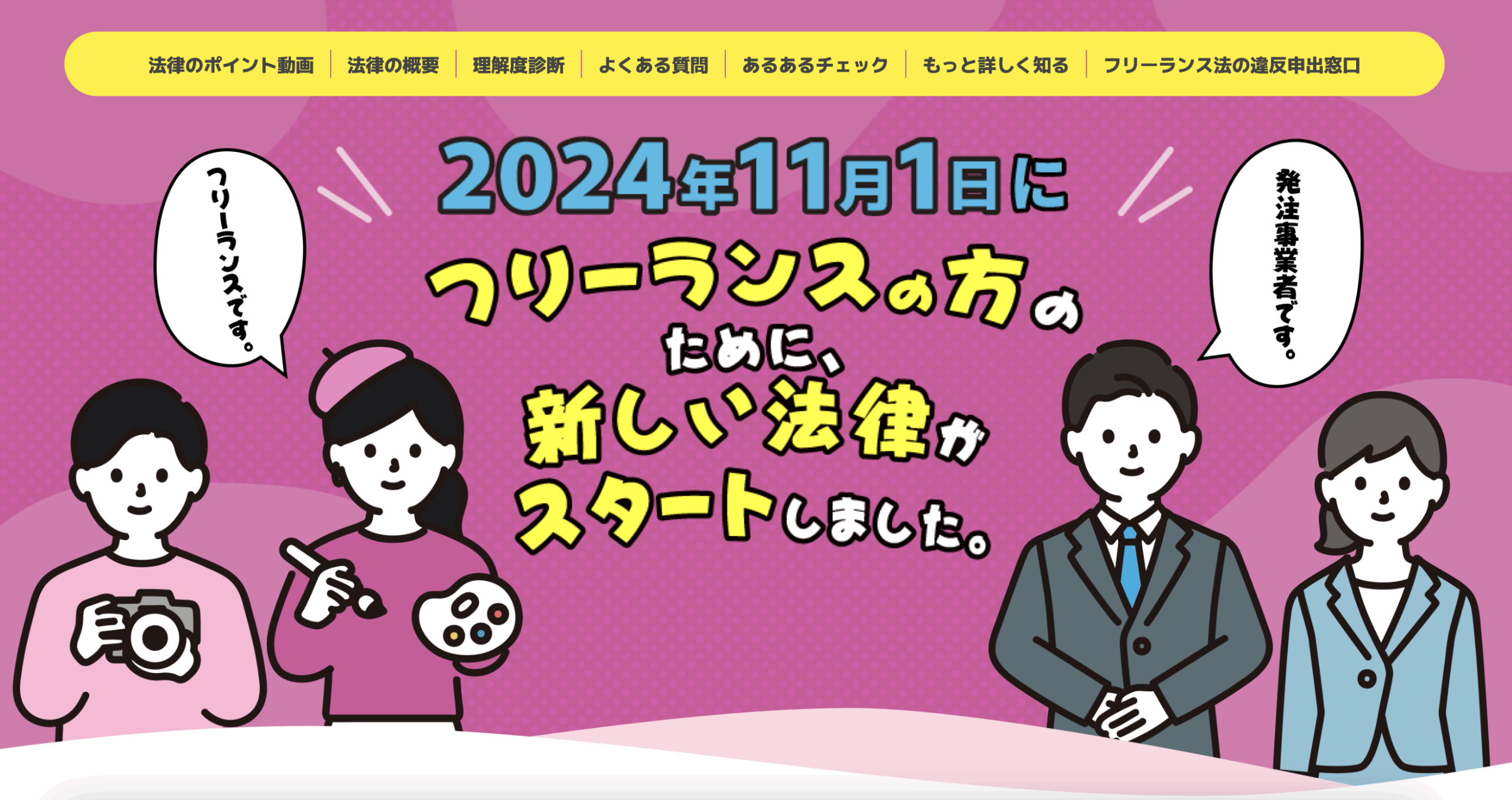フリーランス法とは?音楽家さんが身を守る方法を伝授します♪/Vol.19
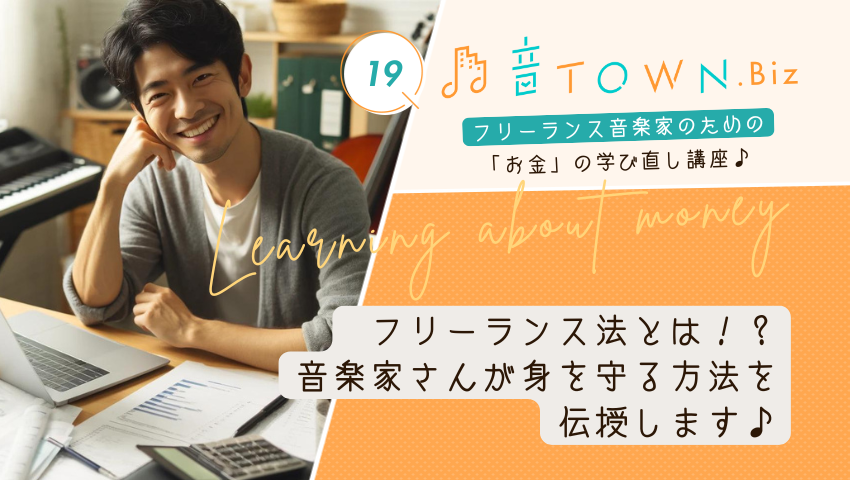
2024年11月1日、「フリーランス法」(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)と呼ばれる新しい法律が施行されたのをご存知でしょうか。
約2ヶ月前、某大手の音楽教室がこの法律に違反したとして、公正取引委員会が是正勧告をしたニュースが比較的大きく取り上げられましたよね。
(皆さんがよく知っている大手です。気になる方は「大手音楽教室 フリーランス法 違反」のようなワードでググってみてください)
僕はここの講師を務めた事はないものの、「楽器店でのデモ演奏」や「店員さん向けの営業の講習・研修」などを依頼された事があり、また、周囲にも講師の知り合いが何人かいるので、ちょっとショックだったというか、それ以上に「同業者として恥ずかしい」「呆れた」という感想が正直なところかもしれません。
これまで泣き寝入りだった問題が浮き彫りになるきっかけになったという点では、立場の弱いフリーランスの音楽家さんにとっては「フリーランス法」の施行は朗報と言えるのではないでしょうか。
今回はこの法律について極力分かりやすく解説すると共に、僕が考える「トラブルに巻き込まれないための自衛の方法」をお伝えしようと思います♪
※法律家ではないため、あくまで「フリーランス音楽家経験者」「一人会社・音楽教室などの経営者」の視点で言及しています。
『音TOWN』(おんたうん)は、『音楽“と”生きる街』をコンセプトに、(プロアマ問わず)音楽家がより生きやすくなるために、主に音楽以外の有益な情報をお届けしています。 →詳しくはコチラ
このシリーズでは、音楽を職業にしていくためにとても重要であるにもかかわらず、学校ではあまり教わらない“お金”について、改めて学んでいきましょう!お金について学ぶと「生き方」も明確になりますよ! →詳しくはコチラ
この記事を読むと役に立つ人は!?
・フリーランス・個人事業主の音楽家(演奏家)として活動している方
・昨年施行された「フリーランス法」がよく分かっていない方
・お金や仕事内容で事務所や友人と揉めたくない方
読んだらどんな良い事が!?
・「フリーランス法」の概要が分かる
・法的な知識を超えて「自分の身を守る方法」が分かる
・結果、収入アップや幸福度アップにつながる可能性がある
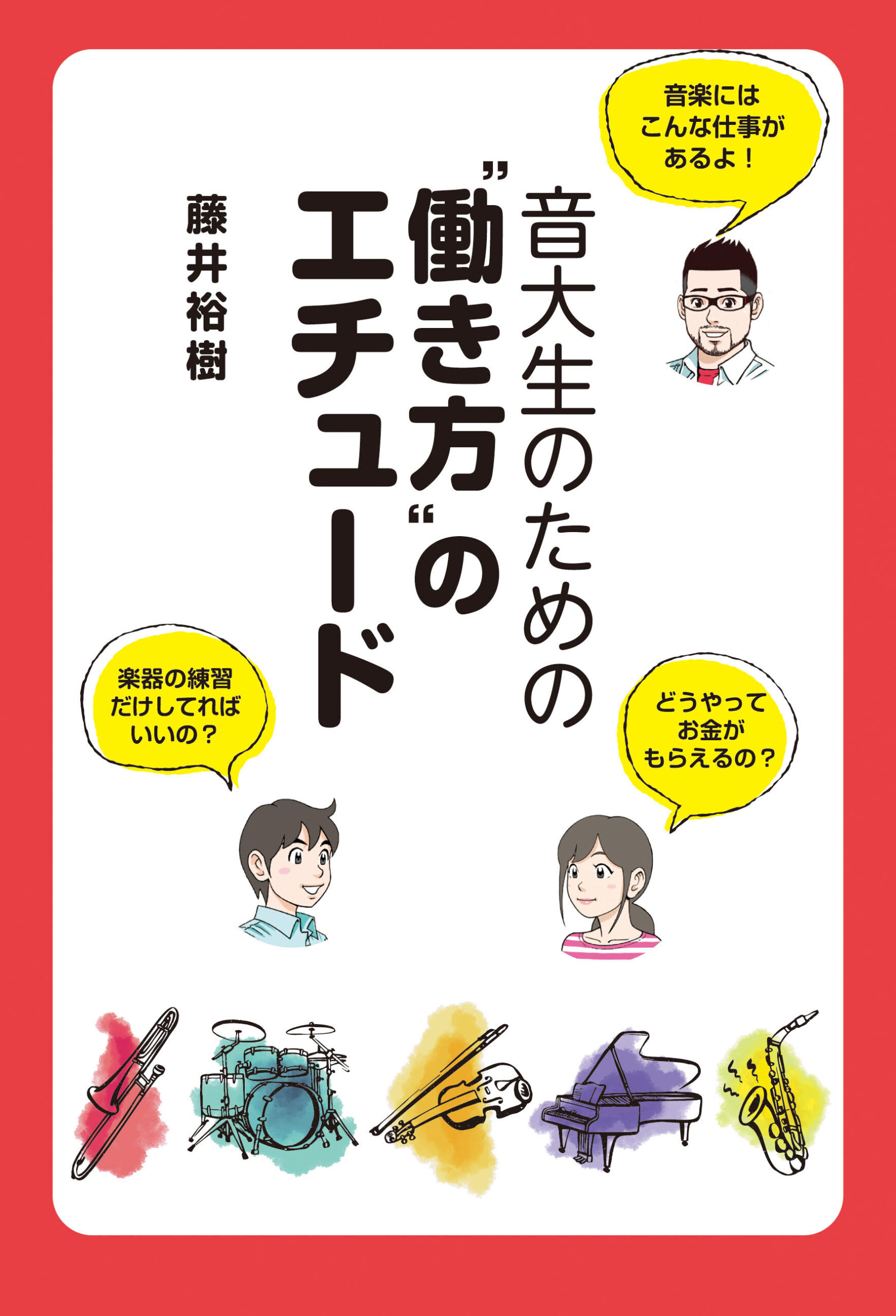
フリーランス法(フリーランス新法/保護法)とは!?
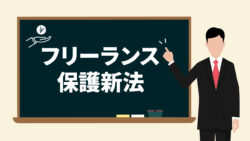
フリーランス法は、主にフリーランスが安心して働ける環境を整備し、受注者と発注者の取引(報酬や仕事内容)を適正化する事を目的として制定された法律です。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランス法・フリーランス新法・フリーランス保護法といった呼び方もあるようですね。
「受注者」の定義
仕事を受ける、もらう側のフリーランス(個人事業主)の音楽家さんは「受注者」で、「特定受託事業者」と呼びます。
ちなみにこの法律の場合、従業員を雇っていない、いわゆる「一人社長(会社)」も含まれるそうです。
「発注者」の定義
仕事をお願いする事務所側、つまり「発注側」は「特定業務委託事業者」と呼びます。
従業員を雇っている音楽教室、音楽事務所、イベント企画会社、レコード会社などが該当しそうですね。
下請法との違いと改善点
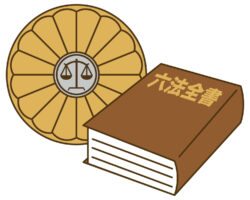
「フリーランス法」の施行前は「下請法」という法律だったようですが、どのように変わった(改善された)かと言うと、
1. 保護対象の違い

下請法:発注者の資本金が1,000万円以上の場合に適用(発注者が小規模事業者だと規制の対象外になる事が多かった)。
フリーランス法:資本金の額に関係なく、「2人以上の役員がいる法人」や「従業員を使用する法人および個人事業主」も規制の対象に含まれるように!
2. 業務範囲の違い

下請法:適用範囲は「モノを作る・修理する・プログラムを作る」など、特定の“仕事の種類”に限られていました。
例えば音楽家さんの場合、「作編曲をして納品」などはOKだったけど、「演奏依頼」や「音楽レッスン依頼」といったサービスは対象外だったという事でしょうか。
フリーランス法:仕事の種類や目的を限定せず、どんな業務委託でも原則OKに!
つまり、「作編曲」のような制作関係だけでなく、「演奏依頼」や「レッスン・講師業務」など、音楽家さんが受注する仕事のほとんどが対象になりました。
3. 契約方法の違い
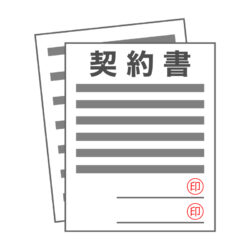
下請法:契約内容(報酬や仕事内容)は、基本的に紙の契約書や発注書で渡すのがルール。
「メールで送っておきますね」ではダメで、どうしてもメールにするなら事前に「契約書はメールでやり取りします」と合意しておく必要があったそうで、そのため、短期間の仕事や小規模な依頼では、手続きが面倒になりがちでした。
フリーランス法:契約書は紙に限らず、「メール」「LINE」「メッセンジャー」など、電子的なやり取りでもOKになりました!
例えば「この演奏依頼の謝礼は3万円で◯月◯日までにお願いします」とLINEで送られてきても契約として有効になり、保護の対象になるというわけですね。
『フリーランス法において明示する必要がある取引条件』
・業務の内容
・報酬額
・支払期日
・発注事業者の名称
・業務委託日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
4. 支払い期限の違い

下請法:「支払いは遅らせてはいけません」とだけ決められていて、具体的に「何日以内」とは書かれていなかったそうです。
そのため、発注者が「じゃあ半年後に払うよ」なんて極端な条件を契約時に入れてしまえば、形式上は違反にならないケースもあったんだとか。
フリーランス法:発注者が成果物(演奏・楽譜・音源など)を受け取ってから「60日以内」に支払う事が義務になりました!
さらに、発注者が別の下請に再委託する場合は「30日以内」が目安とされています。
つまり、契約時に「支払いは半年後」などの不合理な条件は設定できなくなり、「いつまでにお金が振り込まれるかが明確になった」というわけですね。
※ちなみに作編曲のようなお仕事をされていない方は「成果物」という言葉自体がピンとこないかもしれませんが、「演奏依頼」の場合、「演奏を行った日(本番当日)」、「レッスン」の場合は「レッスン当日」が「発注者が成果物を受け取った日」となります。
5. 禁止行為の範囲

どちらも受領拒否、報酬減額、不当変更を禁止していますが、新法はさらに「ハラスメント防止」や「育児・介護への配慮」など、働く環境全般にも踏み込んでいます♪
フリーランスの音楽家さんはどうやって身を守る!?

働き方が多様化し、音楽家さんに限らず「フリーランス」の方が増え(声優・デザイナー・イラストレーター etc.)、また、そこから「搾取してやろう」という比較的大規模な会社、事務所なども増えた事から、いわゆる「弱者」である「フリーランス」や「一人社長」を守ろうという流れで「下請法」から「フリーランス保護法」へと変更された事が分かりますね。
ちなみに僕はこれまで約25年間、フリーランス(個人事業主)または一人社長(会社)だったわけですが、大きなトラブルはほとんど無いと言って良いかと思います。
何公演かまとめて行った芸術鑑賞教室の演奏料や、大手レコード会社所属のアーティストのテレビ出演のサポートのギャラがなかなか入金されないくらいはありましたが、法的措置などではなく、催促の結果、回収できました。
どちらかと言うと、相手が「フリーランス保護法」で言うところの「特定業務委託事業者」ではなく、同業者の友人・知人や先輩から来た仕事のほうが「事前にギャラの提示がない」とか「現場に行ってみたら聞いていたよりはるかに拘束時間が長い」とか「拘束時間が増えたのにギャラは変わらない」といった問題が多かったようにも思いますね。
トラブルの相手が個人事業主の友人・知人、一人社長(会社・事務所)の場合、「フリーランス法」は適用にならないと思うので、やはり原則は「自衛」じゃないでしょうか?
1. お金・ビジネスの知識、スキル、マナーを身に付ける!

僕が思う最大・最良の身の守り方は、この「音TOWN.Biz」でお伝えしているような『お金・ビジネスの知識、スキル、マナーを身に付ける事』!
周囲の音楽家さんを見ていても、そもそも自分のギャラが適正か(時間や内容に見合っているか)よく分かっていない方が結構多いです。
こういう方は「おかしいと思っても交渉ができない」か、もっと言うと「おかしい事にも気付いていない」。
本来であれば「法律を持ち出す以前に解決する」か、「そもそも問題が起きないほうが良い」に決まってますよね!
冒頭で取り上げた大手楽器店の問題のように、すでに問題が起きている時点で間違いなく「気持ち良く仕事ができていない」のですから、できれば起きる前に防ぎたいものです。
(「訴訟」はストレスそのものですし、数万円のトラブルで弁護士さんに相談していたら元が取れない、結果「泣き寝入り」せざるを得ない可能性が高い)
この大手楽器店の講師を務めている友人に「報酬(マージン)は何パーセントなの?」と聞いた事があるのですが、その方は答えられませんでした(「分からない」「知らない」という回答でした)。
面接や契約の段階でそういった話も出ていない(もしくは契約書を読んでいない・理解していない)という事だし、事務所を通した演奏のギャラと違って、お客様(生徒さん)のレッスン料がいくらで、入金されている金額がいくらか分かっていれば(報酬明細を見れば)自分で計算出来るじゃないですか。
厳しい言い方かもしれませんが、この場合「どっちもどっち」。
「搾取する側は搾取しやすそうな人を雇う」というのはそれなりに的を射ているのではと感じます。
『フリーランス音楽家のための分かりやすい「請求書」の書き方【前編】/Vol.11』
(参考:「音楽家さんが“ナメられない”ために!」)
『フリーランス音楽家が知っておいてほしい「確定申告支払調書」の話/Vol.6』
(参考:「税の知識やお金の管理も仕事の一部!」)
例えば上記の記事でもお伝えした「請求書の書き方」を知らないとか「税の知識」があまりに乏しいと、「搾取される側」に陥りやすいと思います。
※現場で終演後などに、もしも発注者が報酬について何も触れてこない場合、「お支払いはいつ頃になりますか?」や「請求書の提出は必要ですか?」などは受注者側から話題にしたほうが良いですね。
後日の請求書の提出が必要ない場合、当日「支払い指示書 兼 請求書」のような先方が作成した書類に記入や捺印するのが普通です(先方に振込先などの情報を伝えなければ入金されるわけありません)。
2.「口約束」で仕事を受けるのをやめる!(必ず記録を残す!)

以前、若い音楽家のサポートを行っていたNPO法人向けにも下記のようなブログを書いた事があるのですが、「フリーランス法」云々の前に、普段から「口約束をしない」、「LINEやメッセンジャーでやり取りを記録に残す」などをやっていれば、相手も「この人は慎重だから搾取はできない」となりますよね。
・法律に守ってもらうのは最終手段!
・その前に自分自身の行動で身を守る!
というのが最も現実的、効果的ではないでしょうか?
『下請法との違いと改善点』(3.契約方法の違い)でお伝えした「フリーランス法において明示する必要がある取引条件」は、あくまで「法律上」の話。
音楽家さんにとって実用的かと言われると、そうでもないかもしれません。
LINEやメッセンジャーのやり取りだったとしても「日時」「拘束時間」「ギャラ/報酬の金額(内税か外税かまで)」くらいは最低限事前に把握し、証拠を残しておいたほうが良いでしょう。
僕の経験上、一番曖昧になるのが「拘束時間」ですね。
例えば、「当日のみという約束だったのに、後からリハが1日追加された」とか「(イベントなどで)出演時間が夜だと聞いていたのに、入り時間が午前だと後から言われた(長時間現場で拘束される事になった)」という事例。
これって、もしもギャラがそのままだったら(時給換算したら)、報酬金額が実質半分になっている可能性もあるじゃないですか。
「夜の本番だから入り時間は夕方くらい。じゃあ午前中からお昼過ぎまでレッスンの仕事を入れよう」なんて事はよくあると思います。
その仕事が受けられなくなるのですから(機会損失)、後出しであまりにも不当な条件を提示された場合、異議を申し立てる権利はフリーランス側にもあるはずですよね。
参考:「株式会社マウントフジミュージック」の正式依頼フォーム
※僕の会社のいわゆる「契約書代わり」です。
どこまで採用するかは各自のご判断ですが、こういった項目を確認し、証拠の残るメール等でのやり取りにしておけば、後で揉める可能性は低く、揉めたとしても「こういう約束でしたよね?」と伝えられるので、交渉を有利に進められると思います!
3. 理不尽なお付き合いのお仕事は断捨離する!

時代は変わってきています(今は「昭和」ではありません)。
「(あの人から/あの事務所から)仕事が来なくなったらどうしよう?」
などと不安になり過ぎずに、
「理不尽な事務所や先輩からの仕事、やりたくない仕事は断る」
「(ワンクッション置いて)断る前に一度“理路整然と”意見を伝える・交渉する」
勇気をもちましょう!
「今よりも良い仕事がしたい、収入を増やしたい」と考えている場合、大抵は求めるだけ(足し算・執着)ではダメで、何かしら「引き算・断捨離・デトックス」をし、自分自身に「余裕・スペース」を作らないと新しい流れは生まれない(理想のお仕事は入ってこない)と思います。
また、人間関係の場合(お仕事もプライベートも)、どちらが正しい、間違っているの観点だけでなく、単純に「相性」の問題(価値観の違い)もあるので、
「合わない相手との関係を切る事が出来て良かった!」
「これでさらに良い仕事が入ってくる!」
とポジティブに捉えられると良いのではないでしょうか。
「サステナブル(持続性)」や、下記の記事でご紹介した「クオリティ・オブ・ライフ(QOL)」、「ウェルビーング(Well-Being)」の観点でも、合わない関係性は手放し、ストレスを減らし、継続的に心身が健康な状態を心がけたほうが幸福な(音楽)人生になると思いますね。
お伝えしたように、基本は「自分の身は自分で守る」のが大切ですが、もしも困り事、揉め事がある場合、僕の経験などからはアドバイスはできますので、ご連絡ください!
※もちろん、法律相談は出来ません!
音TOWNプロデューサー/株式会社マウントフジミュージック代表取締役
3級ファイナンシャル・プランニング技能士/トロンボーン奏者
『藤井裕樹』による『音楽家(ミュージシャン)のための「お金」「キャリア」相談受付中♪』
→詳細はコチラ
万が一どうしようもないレベルの場合は、やはり専門の弁護士さんに相談されると良いと思います♪
Cozy Tazunoki:「弁護士 兼 ハードロックドラマー」破天荒・異端の生き方♪
参考:2024年公正取引委員会フリーランス法特設サイト
※「違反申出窓口」も設置されているようです♪
藤井裕樹/音TOWNプロデューサー
【株式会社マウントフジミュージック代表取締役社長・『音ラク空間』オーナー・ストレッチ整体「リ・カラダ」トレーナー・トロンボーン奏者】 1979年12月9日大阪生まれ。19歳からジャズ・ポップス系のトロンボーン奏者としてプロ活動を開始し、東京ディズニーリゾートのパフォーマーや矢沢永吉氏をはじめとする有名アーティストとも多数共演。2004年〜2005年、ネバダ州立大学ラスベガス校に留学。帰国後、ヤマハ音楽教室の講師も務める(2008年〜2015年)。現在は「ココロとカラダの健康」をコンセプトに音楽事業・リラクゼーション事業のプロデュースを行っている。『取得資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士/音楽療法カウンセラー/メンタル心理インストラクター®/安眠インストラクター/体幹コーディネーター®/ゆがみ矯正インストラクター/筋トレインストラクター』