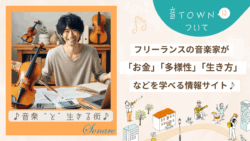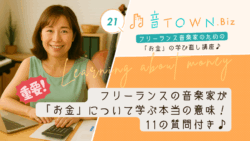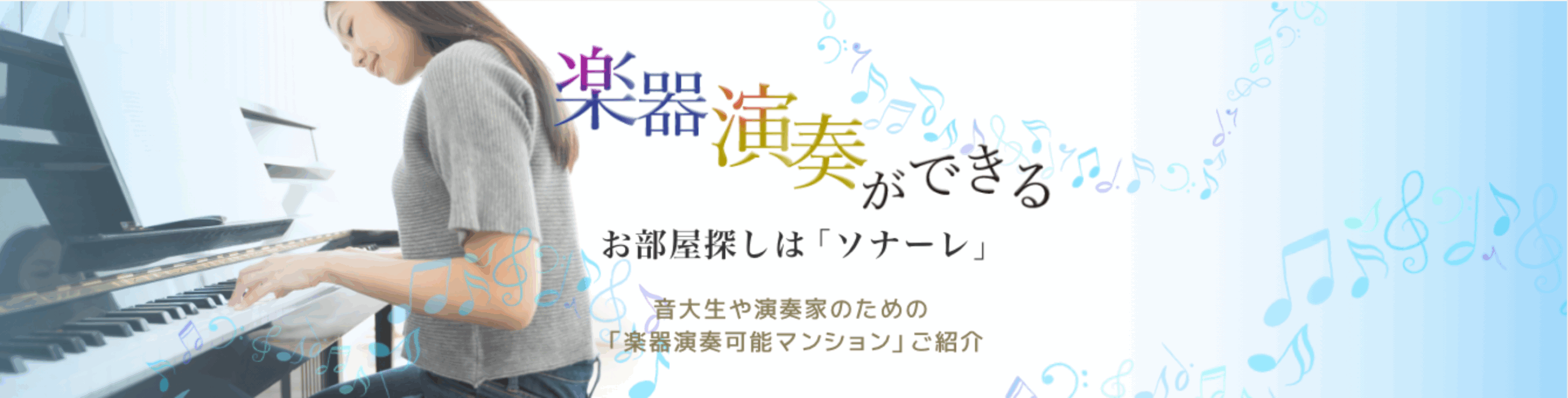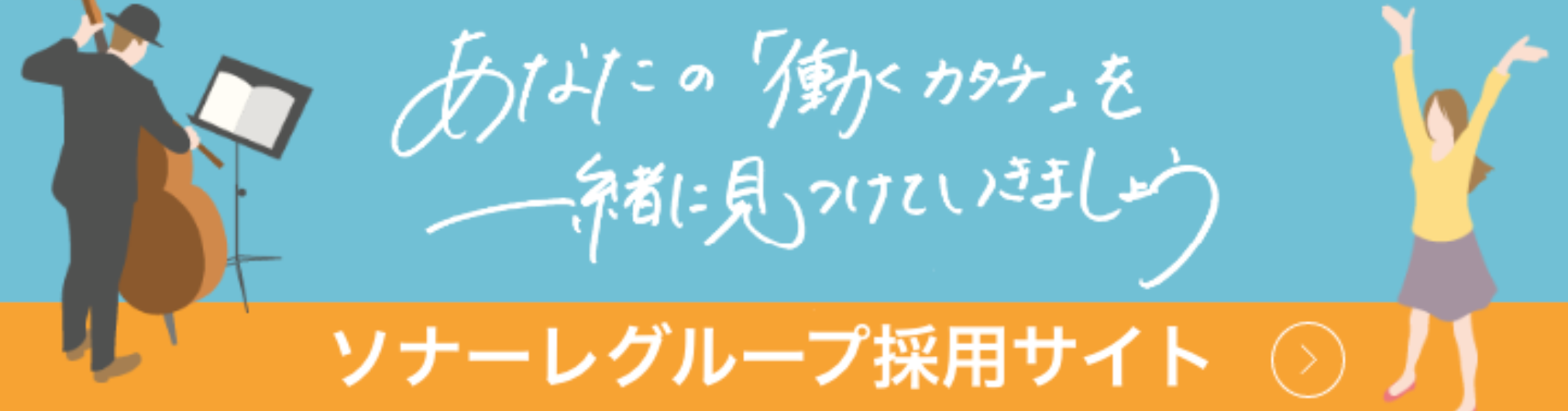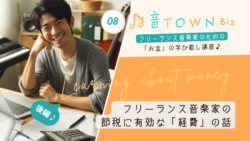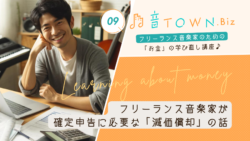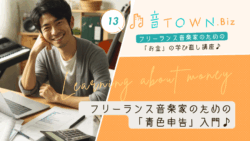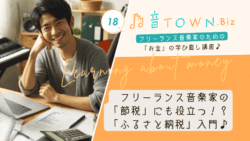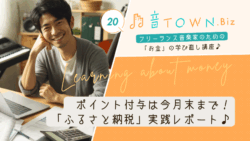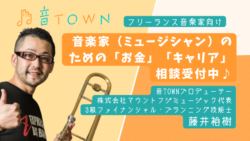フリーランス音楽家が確定申告に使える「控除」の話/Vol.10
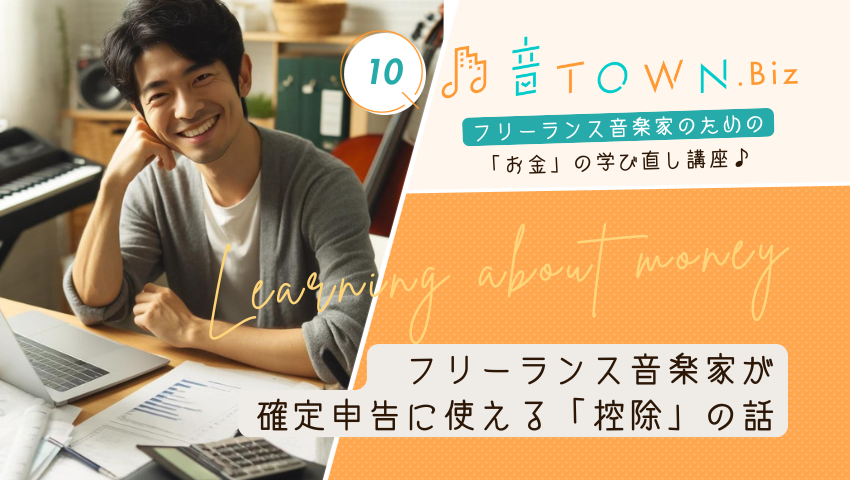
今年は2月17日に確定申告が始まりました(3月17日まで)。
ここからの約1ヶ月はフリーランスの音楽家さんには憂鬱、面倒な時期と言えるかもしれませんね。
これまで「音TOWN.Biz」では、「確定申告の基本」から「必要経費」「減価償却」について学んできましたが、今回解説する「控除」もめちゃくちゃ重要です!
使える「控除」は全部使って、しっかり節税しましょう!!
昨年6月から始まった「定額減税」についても少しだけ触れていますので(1人につき「所得税3万円・住民税1万円 = 合計4万円」が減税されるので)、ぜひ最後までお読みください♪
『音TOWN』(おんたうん)は、『音楽“と”生きる街』をコンセプトに、(プロアマ問わず)音楽家がより生きやすくなるために、主に音楽以外の有益な情報をお届けしています。 →詳しくはコチラ
このシリーズでは、音楽を職業にしていくためにとても重要であるにもかかわらず、学校ではあまり教わらない“お金”について、改めて学んでいきましょう!お金について学ぶと「生き方」も明確になりますよ! →詳しくはコチラ
この記事を読むと役に立つ人は!?
・フリーランス・個人事業主の音楽家(演奏家)として活動している方
・初めて確定申告を行う方
・毎年確定申告を行っているが、実は仕組みをよく分かっていない方
読んだらどんな良い事が!?
・確定申告の基本が理解できる
・控除がどういうものなのか分かる
・還付金を増やし、所得税・住民税を下げ、節税出来る可能性がある
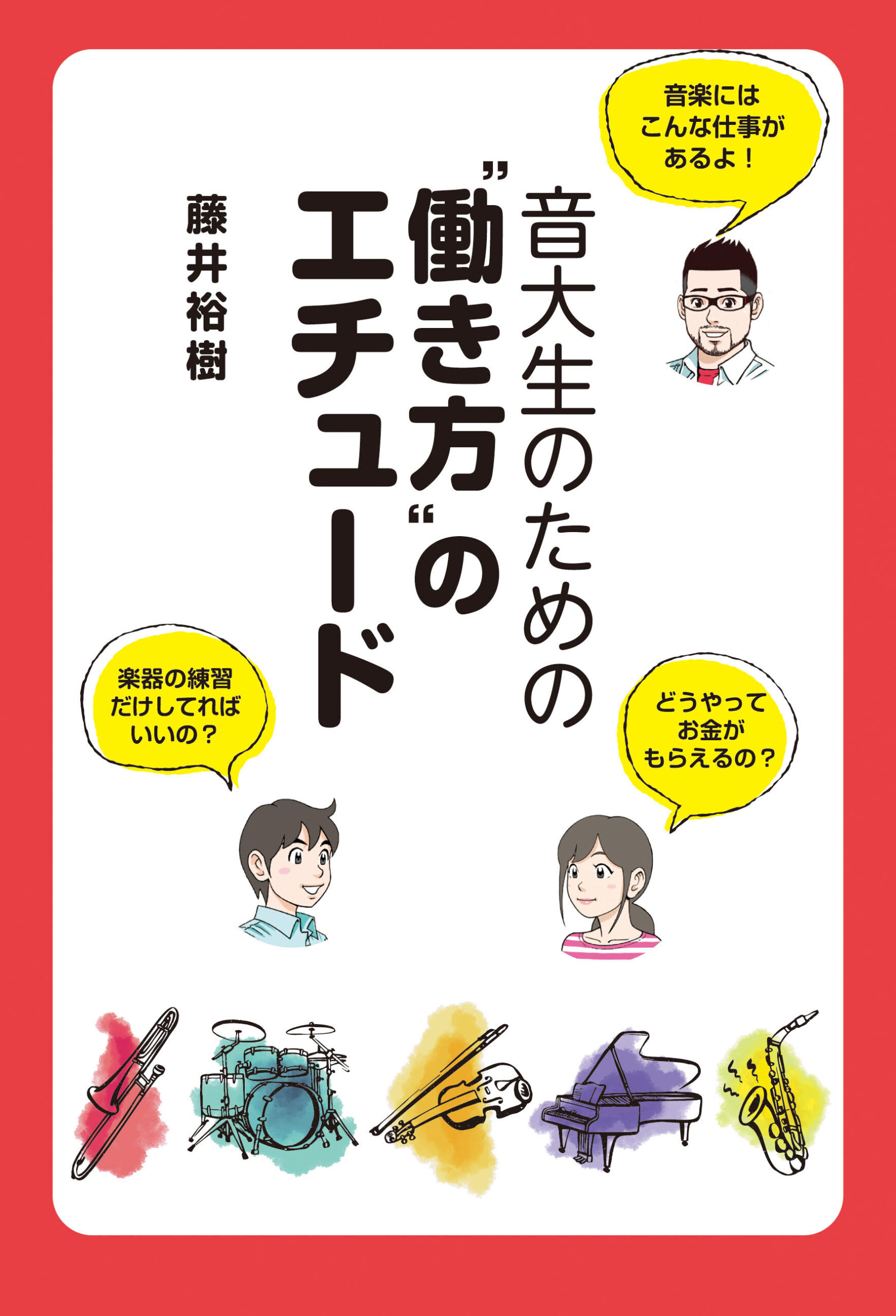
控除って何?

「控除」とは、「差し引く」という意味の言葉で、税制で使われる場合は「一定金額を差し引いて納税額を減らす事」を指します。
控除を適用できれば、その分、納税の負担を軽減(節税)できる事になりますね!
例えば、旦那さんが奥さんやお子さんを養っている場合、一般的には独身の方よりもお金がかかるじゃないですか。
ですので、「所得から一定金額を引いてあげて、納税額の負担を減らしてあげますよ」みたいな制度です。
控除は大きく分けて2種類
皆さんがこの時期に行っている「確定申告」は「所得(税)の申告」でしたよね。
(所得の金額によって「住民税」の額も決まりますが、申告をしているのは「所得税」です)
所得税の確定申告で適用出来る控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。
所得控除
所得金額から一定額を差し引く事です。
ちなみに「所得」とは「収入(売上)から必要経費を引いたお金」の事でしたね。
まず1年間の「売上」を計算し、そこから「必要経費」を引き、「減価償却」できるものも引いて導き出された金額(所得)から、さらに差し引く事ができるのが「所得控除」です。
※「必要経費」「減価償却」が分からない方は下記の記事で復習してください♪
フリーランス音楽家の節税に有効な「経費」の話【前編】/Vol.7
税額控除
税額から直接一定金額を差し引く事です。
つまり、収入(売上)から「経費」を引いて、「減価償却費」も引いて、「所得控除」も行って導き出された(所得)税額から、さらに差し引く事ができるお金。
※「所得控除」と「税額控除」はどちらも税額を下げる事ができますが、節税効果は一般的に、「税額控除」のほうが大きくなります。
所得控除の種類
基礎控除

合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも「48万円」が控除されます。
(関係のある方はほぼいらっしゃらないと思いますが、2,400万円〜2,450万円以下は32万円、2,450万円〜2,500万円以下は16万円、2,500万円以上の方は適用なし)
ちなみに、「白色申告」ではなく、「青色申告」の場合、この基礎控除48万円とは別に「青色申告特別控除」(最大65万円)が適用になり、併用が可能なため、最大で113万円が控除されます。
これまでも時々触れているように、「青色申告」にはさまざまなメリットがありますので、後日改めて解説しますね♪
配偶者控除
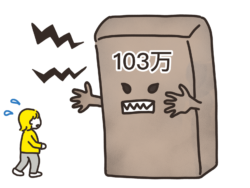
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、「控除対象配偶者」がいる場合、最高「38万円」(合計所得金額が900万円以下の場合)が控除されます。
対象は「民法の規定による配偶者」がいる場合ですね。
国税庁のHPなどを見ると、聞き慣れない言葉ですが、「納税者本人と生計を一にしている」(内縁関係は対象外)とあります。
「納税者本人と生計を一にしている」は、例えば「同居の奥さんがいる」とか、仮に単身赴任で同居をしていなくても、生活費の仕送りをしている奥さんがいれば「生計を一にしている」となるようです。
もう一つの大事な点は「配偶者の合計所得金額は48万円以下でないといけない」(給与所得の場合は年収103万円以下)という事!
例えば旦那さんがフリーランスの音楽家さんで、奥さんがパートアルバイトで(報酬ではなく)給与をもらっている場合、年収が103万円を超えてはダメですよ!という話ですね(給与所得控除が55万円なので、103-55=48万円)。
※昨今「年収103万円の壁」という言葉をニュースでよく耳にすると思いますが、103万円を超えると、この「配偶者控除」や後ほど解説する「扶養控除」の対象から外れてしまうため、少子高齢化などで人材不足になっているにも関わらず、103万円以内に収入を抑えるため、「働き控え」が起きているという問題です(国民民主党が、この103万円の引き上げを公約に掲げて動いているので、近々変更になる可能性が高いと思います)。
ちなみに『音TOWN』をご覧になっている方の中には、「夫婦でフリーランスの音楽家さん」というパターンの方も多いと思います。
この場合も、「どちらか一方の合計所得金額が48万円を超えていると、もう一方の納税者の配偶者控除の対象にはならない」という事になりますが、次に解説する「配偶者特別控除」が使える可能性が高いと思います。
配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円〜133万円以下の場合、先述の控除対象配偶者の所得以外の要件が満たされていれば、納税者本人と配偶者の合計金額に応じて、最高「38万円」の控除を受ける事ができます。
夫婦でフリーランスの音楽家さんであっても、奥さんがパートで103万円以上稼いでしまったとしても、所得が133万円以下であれば控除があるという事ですね!
(配偶者控除が使えなくても、配偶者特別控除で段階的に減税が可能!)
※控除額の分類がかなり細かいので、気になる方はネットで調べたり、税務署に問い合わせてみてください♪
扶養控除

納税者本人に「控除対象扶養親族」がいる場合に控除を受ける事が出来ます。
要件は、先ほども出てきた言葉ですが、「納税者本人と生計を一にしている」16歳以上の親族、合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)などがありますね。
また、親族の年齢によって「一般の控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」に分類され、控除額が変わります。
16歳未満→対象外
16歳以上〜19歳未満→「一般の控除対象扶養親族」38万円
19歳以上〜23歳未満→「特定扶養親族」63万円
23歳以上〜70歳未満→「一般の控除対象扶養親族」38万円
70歳以上→「老人扶養親族」58万円(同居老親等)or 48万円
19歳以上〜23歳未満の控除額が大きくなっているのは、この年代は「お子さんが大学に通っている場合が多く、学費などが大変だから税を優遇しましょう」という事ですね。
例えばお子さんが親御さんに内緒でアルバイトをしていて、うっかり103万円を超えてしまうと、この「特別控除」が受けられなくなり、親御さんの納税額が増えてしまうので、高校生や大学生のお子さんがいらっしゃる方は特に気をつけてください!
16歳未満が対象外になっているのは、「児童手当」という別の優遇制度があるからです。
申請をしないともらえないので、対象年齢のお子さんがいらっしゃる場合は必ず申請をしましょう!
あまり知られていないかもしれませんが、扶養はお子さんだけでなく、高齢のお父さんやお母さんの面倒を見ている場合も対象になる可能性があるので、該当している方はさらに詳しくネットで調べたり、税務署などに相談してみてくださいね。
社会保険料控除
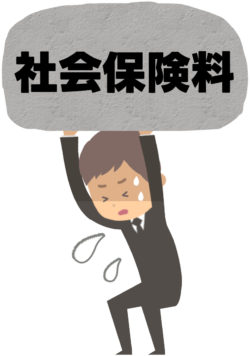
フリーランスの場合、「国民健康保険料」「国民年金保険料」の他、40歳以上の方は加入義務のある「介護保険料」、任意で加入している場合「国民年金基金料」の全額が控除の対象となります。
生命保険料控除

一定の生命保険料を支払った場合に控除する事ができます。
控除の区分と最高控除額(限度額)は下記の通り。
一般生命保険料控除→「所得税」40,000円/「住民税」28,000円
個人年金保険料控除→「所得税」40,000円/「住民税」28,000円
介護医療保険料控除→「所得税」40,000円/「住民税」28,000円
制度全体の所得控除→「所得税」120,000円/「住民税」70,000円
※一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。
※2011年12月31日以前に契約を締結している場合は上記と異なります。
小規模企業共済等掛金控除

納税者本人の「小規模企業共済」や「確定拠出年金(iDeCo)」の掛け金などを支払った場合、掛金の全額が控除されます。
「社会保険料控除」「生命保険控除」「小規模企業共済等掛金控除」についてはこの記事でも詳しく説明しているので、参考にしてみてください!
フリーランス音楽家に有益な「私的年金」を活用した「節税」テクニック/Vol.5
地震保険料控除

自宅建物や家財を保険の対象とする地震保険料を支払った場合、「最高5万円」まで、保険料の全額を控除できます。
医療費控除

本人や、納税者本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費等を支払った場合、一定額を超えると控除を受ける事ができます。
1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に限ります。
「支出した医療費」-「※保険料などの金額」-「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額」=『医療費控除額』(上限200万円)
※は健康保険や生命保険、医療保険から補填される給付金など
医療費であっても「美容整形はNG」とか、「人間ドックや健康診断はNGだけど、それによって、癌などの重大な疾病が見付かって治療を行った場合はOK」「通院のための交通費もOKの場合とNGの場合がある」など、細いルールがあるので、対象の金額以上の医療費を支払った方は細かく調べてみると良いでしょう。
その他
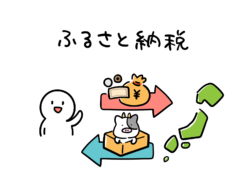
関係のある方は少ないと思いますが、以下も「所得控除」ですので、該当する方はネットで調べたり、税務署などに問い合わせてみてください。
「障害者控除」→納税者本人または扶養親族が障害者である場合に受けられる
「寡婦控除」→離婚や死別によって夫がいない女性が受けられる
「ひとり親控除」→所得が500万円以下で扶養する子どもがいる「ひとり親」が受けられる
「勤労学生控除」→学生が働いて得た所得が75万円以下なら27万円の所得控除を受けられる(学業を続けながら働く学生を支援するための制度)
「雑損控除」→災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に受けられる
「寄附金控除」→特定の団体に寄付をした場合に受けられる(ふるさと納税や公益法人への寄付)
※「ふるさと納税」は最近CMなどでもよく宣伝していて、利用している方がそれなりにいらっしゃるかもしれないので、後日改めてまとめてみようと思います。
税額控除の種類
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
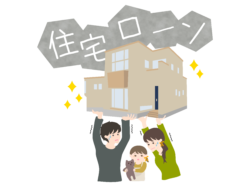
「税額控除」の中で、フリーランスの音楽家さんが一番該当しそうなものは、この「住宅ローン控除」でしょうか(僕の周りでも、結婚してお子さんができて、賃貸ではなくマイホームを購入されている方は結構いらっしゃいます)。
「住宅ローン」を利用して住宅を取得(または増改築)した場合、一定の要件を満たせば、所得税などの税額控除を受けられます(住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じて求めた金額を控除額の上限として、適用期間中、所得税などから控除できます)。
「控除率」は年末のローン残高の0.7%、「控除期間」は最大で13年間。
自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合、「住宅耐震改修特別控除」という別の控除が適用になるようです。
外国税額控除

日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額が控除されます。
個人レベルではあまりないと思いますが、事務所を通さずに海外で演奏の仕事を行い、その国でも所得税を支払わないといけないといった場合、日本との二重課税にならないように調整し、控除されるような仕組みのようです。
配当控除
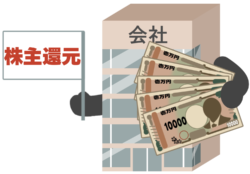
こちらもあまりいらっしゃらないと思いますが、国内株式等の配当等について、総合課税分として確定申告をした場合に控除を受けられます。
※総合課税とは、「事業所得」や「雑所得」など、複数の所得の区分を合計して申告する方法。
フリーランスの音楽家さんの場合、音楽の仕事でのギャラ(事業所得)以外に、株の配当(配当所得)、アパートやマンション経営もしていて家賃収入(不動産所得)などがあり、それらを合算して確定申告をすると「総合課税」になります。
その他

上記以外にも「政党等寄附金特別控除」「認定NPO法人等寄附金特別控除」「公益社団法人等寄附金特別控除」など、かなり細かく、たくさんの「税額控除」があるようですが、多くの方は関係がないように思います。
「ふるさと納税」に関しては、「所得控除の場合」、「税額控除の場合」とがあるようで、こちらも複雑ですので、また別の機会にまとめてみたいと思います。
まとめ
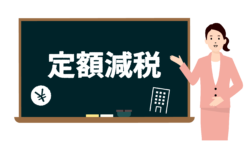
「音TOWN.Biz」では、年明けから集中的に「確定申告」に関する解説を行ってきました。
慣れていない方にはちょっと複雑ですが、今からでも一連の記事を読んでいただいてから確定申告を行えば、所得税や住民税を減らし、還付金を増やせる方も多いのではないかと思います。
また、2024年6月からは「定額減税」という制度が始まり、「所得税3万円・住民税1万円 = 合計4万円」が減税になります(16歳未満の扶養親族も定額減税の対象なので、家族の分も減税になる可能性があります)。
サラリーマンの場合は会社が調整を行い、自動的に減税された分の手取りが増えますが、フリーランスの音楽家さん(個人事業主)は「確定申告」をしないと受け取れないので、忘れずに行ってください!
ちなみに僕は昨年、医療費控除の申告だけ「マイナポータル」を使って確定申告をしましたが(僕は現在フリーランスではなく、役員報酬・給与所得者のため)、随分簡単になっていました。
「e-Tax」や「マイナポータル」でのスマホ申請などは、以前よりもだいぶ便利になってきているのではないでしょうか。
おそらく、今回解説した「控除」なども、数字を入れていけば自動計算してくれるので、手書きよりはるかに楽で間違いにくくになっていると思われます。
これらの説明は、日本中の税理士さんたちがYouTubeで発信をしていますので、
「フリーランス」「個人事業主」「e-Tax」「マイナポータル」「確定申告」「定額減税」「令和6年度」などのワードを組み合わせて検索してみてください。
説明が分かりやすい動画は上位に表示されるので、その中で情報が新しく、ご自身が理解しやすい動画を観ると良いと思います。
※控除はかなり複雑で、説明不足になるため、一応「国税庁」のHPのリンクを貼っておきましたが、個人的には「分かりにくい」と感じます(YouTubeもブログもITスキルの高い税理士さんのコンテンツのほうがオススメ)。
昨今の物価高や円安の状況で、なおかつギャラのアップは見込めない中、確定申告を正確に行い、脱税ではなく、節税という形で所得税や住民税を減らし、手元に残るお金を増やす事はとても大事ですよね!
「“プロ”の音楽家」「事業主」として活動している方には「必須の知識・スキル」と言っても過言ではないので、頑張ってみてください!!
音TOWNプロデューサー/株式会社マウントフジミュージック代表取締役
3級ファイナンシャル・プランニング技能士/トロンボーン奏者
『藤井裕樹』による『音楽家(ミュージシャン)のための「お金」「キャリア」相談受付中♪』
→詳細はコチラ
藤井裕樹/音TOWNプロデューサー
【株式会社マウントフジミュージック代表取締役社長・『音ラク空間』オーナー・ストレッチ整体「リ・カラダ」トレーナー・トロンボーン奏者】 1979年12月9日大阪生まれ。19歳からジャズ・ポップス系のトロンボーン奏者としてプロ活動を開始し、東京ディズニーリゾートのパフォーマーや矢沢永吉氏をはじめとする有名アーティストとも多数共演。2004年〜2005年、ネバダ州立大学ラスベガス校に留学。帰国後、ヤマハ音楽教室の講師も務める(2008年〜2015年)。現在は「ココロとカラダの健康」をコンセプトに音楽事業・リラクゼーション事業のプロデュースを行っている。『取得資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士/音楽療法カウンセラー/メンタル心理インストラクター®/安眠インストラクター/体幹コーディネーター®/ゆがみ矯正インストラクター/筋トレインストラクター』